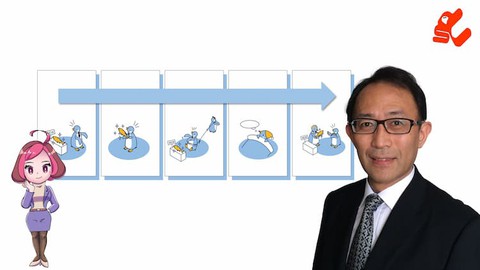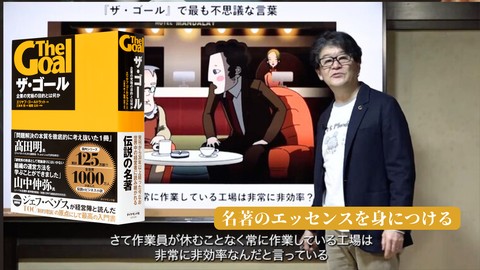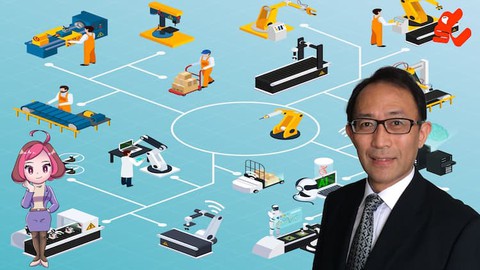【ものづくり革新・改善シリーズ】めざす姿を実現するための改善活動の進め方
同じ目的に向かって一緒に仕事をしている職場やチームが、その目的達成のために、協力して仕事のやり方やツールの改善を行う取り組みを改善活動と言います。協力して、それぞれが役割をもって取り組むためには、同じ改善の枠組みの活動とする必要があります。 このコースでは、職場での改善活動が一体的な取り組みとなるように、職場のめざす姿を明確にし、その実現のために論理的な改善ストーリーに沿って、同じ枠組みと手法を使って、成果を出す組織的改善の進め方とポイントを習得します。 【この講座で学ぶこと(セクション構成)】 ■Section1 めざす姿実現のための改善ストーリー 改善アプローチには、QCストーリーに代表される帰納的アプローチの問題解決ストーリーと、めざす姿を実現するための演繹的アプローチの改善ストーリーがあります。問題解決スーリーは、問題の原因を追究する進め方が特徴ですが、改善ストーリーは、めざす姿の実現のための課題を整理して、解決に向けた改善を行うのが特徴です。ここでは、めざす姿を実現するための改善ストーリーのステップと各ステップのめざす姿の設定、課題分析、改善、効果の測定、定着の内容と取り組み方法を学ぶことができます。 ■Section2 改善の枠組みと手法 職場においてチーム改善を行うためには、改善手法を相互に連携させ、機能させる改善の枠組みを作る必要があります。改善の枠組みは、改善活動の場、活動の見える化、改善のPDCAサイクルを回す仕組み、日々の仕事の見える化と課題の洗い出し、効果の見える化と標準化ができるようにします。ここでは、チーム改善活動のための6つの改善手法と管理手法を組み合わせた改善の枠組みとその実践のためのツールと実践ノウハウを学ぶことができます。 ■Section3 全員参加の改善活動 職場で行う改善活動は、全員参加で行うことが推奨されていますが、その理由は何でしょうか。全員参加の改善活動は、仕事のやり方とツールを改善するとともに、組織力を高めることもできます。組織力とは、個々の能力を組み合わせて相乗効果を発揮させ、個々の能力の総和より大きな力とすることです。ここでは、全員参加の改善の意義を理解し、全員参加による取り組みで知恵の相乗と共有を行い、組織力を高める改善活動の進め方とポイントを学ぶことができます。 ■Section4 改善マインドを高める組織風土づくり 誰もが自分の仕事をより良くしたいと思っていますが、なかなか行動に置き換わってきません。良くしたいという思いが改善行動となるためには、改善マインドを高めていかなければなりません。そして、強い改善マインドは、良い組織風土の上に育ちます。ここでは、改善マインドが育つ良い組織風土をつくるためのバランスの良い価値観の形成と共鳴、共有する方法とポイントを学ぶことができます。 ■Section5 改善効果の導出 改善しても「良くならない」、「効果が出ない」という声を聞くことがあります。本当に効果がなかったのでしょうか。実は、改善効果が見えていないのです。改善効果は見えなくなってしまう3つ理由を認識し、効果の見える化と導出をしなければなりません。ここでは、改善効果が見えなくなる3つの理由である、改善効果が化けること、改善効果が埋もれること、改善効果が小さすぎることに対する対策と測定方法を学ぶことができます。 ■Section6 活動の評価とふり返り 改善活動で効果を出すためには、取り組んだことを評価し、活動を見直すPDCAサイクルを回し、改善活動のレベルアップをしていかなければなりません。目標に対する達成度だけを評価しても活動のブラッシュアップはできません。活動前後の変化から成長度、継続的に効果を出す活動であること、リスクについても評価しなければなりません。ここでは、改善活動のPDCAサイクルを回すためには、目標に対する結果、活動前後の変化、効果を出し続ける力、リスクの増減の4つの視点での評価とふり返りの方法とポイントを学ぶことができます。 【講師について】 200以上のコンサルティングプロジェクトと3万人以上の人材育成実績のあるコンサルソーシングの代表取締役・経営コンサルタントの松井順一が様々な業種・職種における改善実績から培ったノウハウを紹介します。 なお本シリーズは、講座を企画開発したコンサルタントの講師に代わり、講座の進行・解説はレクチャロイド『YUI』がナビゲートします。 【本シリーズ・コースの特徴】 『ものづくり革新・改善シリーズ』とは、「目的の見える化」「課題設定力」「実行力」を高め、業務遂行力の向上に役立つカリキュラムです。製造業・メーカーで用いられるトヨタ生産方式、5S・見える化などの実績ある管理・改善手法を組み込み、製造現場はもちろん、営業・開発・管理間接・サービスなどオフィス業務にも役立つ内容です。 知識を得るための『基本編』、定着度を測る『理解度テスト』、演習で学ぶ『実践編』が基本構成です。(『実践編』のないコースもあります) コースを最後まで受講した際は、全体の理解度をチェックする『確認テスト』もご活用ください。 ダウンロードできる実践帳票などのツールも用意していますので、職場での実践・改善にお役立てください。 複数の領域に関わるテーマの場合、同じセクションが掲載されているコースもあります。予めご了承ください。
【ものづくり革新・改善シリーズ】めざす姿を実現するための改善活動の進め方 Read More »