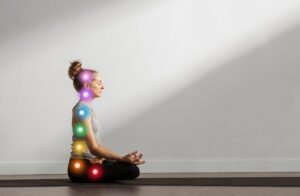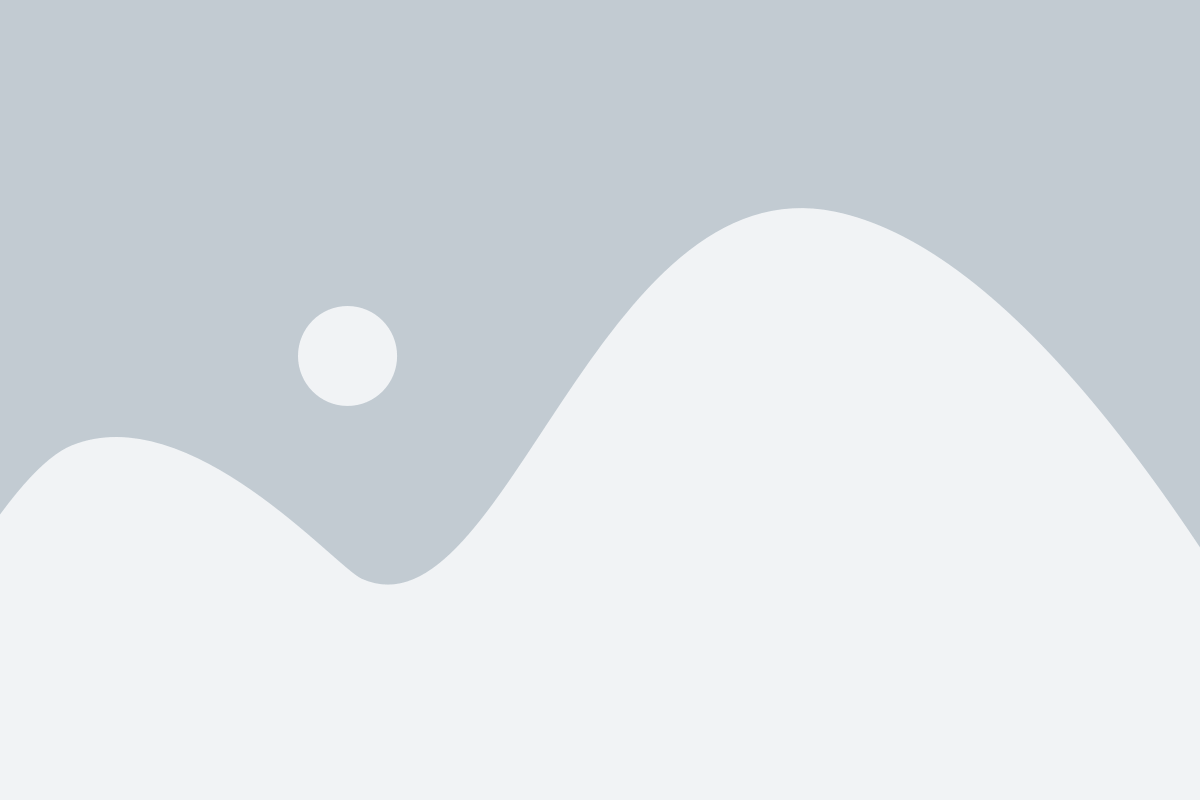こんにちは、講師の飯塚浩也です。
私はこれまで、エンジニアとしての現場経験をもとに、個人の方に2000名以上、プログラミングの上達やChatGPTを活用した業務効率化のお手伝いをしてきました。
2022年11月にChatGPTが誕生し、2023年3月に「GPT-4」が公開され、10月には「GPT-4V」、「DALLE-3」の登場、11月には「GPTs」2024年2月には、「Sora」など、リリースしてからの1年で急激な変化をとげました。そして、この流れは今後も加速していくでしょう。
毎日、仕事やプライベートで忙しく過ごしている皆さまが、この急激に加速した時代を駆け抜け、AI人材として活躍するために必要なスキルを「どこまでもわかりやすく」お伝えします。
このコースでは、「AIの性能を最大限に引き上げ、対話を自由自在に操るプロンプトテクニック」について徹底解説します。
■このコースの概要説明
2024年になると、一部の間で
「プロンプトはオワコン」
という声が上がってます。
AIモデルの性能が大幅に向上したことで、良い出力が返ってくるようになりました。
また、プロンプトの作成自体をAIにさせることが可能になりました。
では私たちは、プロンプトを学ぶ必要はないのでしょうか?
もしあなたが、AIサービスを使う側であるなら、そうかもしれません。
しかし、もしあなたが、AIサービスを作る側であるなら
プロンプトの価値は、今後ますます高くなってきます。
なぜなら、AIサービスの裏側には、必ずプロンプトが入力されているからです。
「AIからの回答をもっとコントロールして、最適化したい」
「他人の作ったプロンプトを改善して、もっと良いものしたい。」
「性能が良いGPTsを自分で作りたい。」
1日で常識が変わってしまう、変化の激しい現代社会において
AIを作る側の立ち位置にいることは
何よりも重要なこと。
本講座では、最短距離で「AIを作る側」になるためのノウハウをお届けします。
【普通のプロンプトしか書けないと、仕事が無くなってしまう?】
「・・・・を教えて」
「・・・・を要約して」
「・・・・を翻訳して」
多くのユーザーが、誰でも書けるようなプロンプトで満足している状況です。
AIで仕事が無くなる人が増えると言われていますが、本講座でライバルに一目置かれるテクニックを学びます。
AIを使いこなして、付加価値の高い仕事を創出できる人材になりましょう。
■コースを受講することで…
応答精度をあげるプロンプトエンジニアリング、PDCAを回すために欠かせないプロンプトの評価方法、AIとの対話体験を向上させるプロンプトデザインスキルが身につきます。
その結果
-
審美眼が手に入り、もう、独自のプロンプト情報に惑わされなくなる
-
プロンプト探しに時間を、消費しなくなる
-
しっかりと評価することで、根拠を持ってプロンプトを改善でき、成果物をブラッシュアップできる
-
AIとの対話を自由自在に調整でき、多くの人に喜ばれるAIサービスを作れるようになる
-
良質なGPTsづくりに活かせて、業務効率化と収益化につなげられる
AIは、自分の優秀なパートナー。
審美眼が養われることで、優秀なAIを見極め、採用できるようになります。
プロンプトについての知見を深め、ビジネスをさらに加速させましょう。
■こんな方が受講に向いています
・自分でうまくプロンプトが作れず、プロンプト探しにいつも時間がかかっている
・ChatGPTの応答精度が悪く、思い通りにいかない
・AI情報収集に苦戦していて、何を信じて良いのか、わからない
・プロンプトの評価方法がなんとなくで、改善がうまくできているか自信がない
・プロンプトによって成果物のクオリティが変動し、回答が不安定になる
・論文を読むコストが高く、海外の最新情報を追うのが大変
■このコースは全部で11セクションです
セクション1:はじめに
セクション2:プロンプトを学ぶ前の必須知識
セクション3:海外論文から学ぶ、プロンプトテクニック前編
セクション4:海外論文から学ぶ、プロンプトテクニック後編
セクション5:プロンプトを評価して、しっかり検証する
セクション6:タスク別にプロンプトを作る
セクション7:汎用的なプロンプトを作る
セクション8:プロンプトデザインで、AI体験を改善させる
セクション9:最前線のプロンプトデザイナーの手法を学ぶ
セクション10:お礼とまとめ
セクション11:ボーナスレクチャー
全部で9時間37分のコースです。
その他、必要に応じてワークシートが用意されています。ワークシートに沿って実践していただくことで、ChatGPTのスキルを高めることができます。
■最後に
本コースに興味をもっていただいた方は、動画終了後に「コース登録」へ進んでください。もっと検討したいという方はプレビューで講座の一部が見れますので、ぜひ講座を覗いてみてください。